津北斎奉閣
みなさんに囲まれた人生を送れて、本当に幸せでした。ありがとう。
この度お手伝いさせていただきました喪家様は、最近では珍しい大家族です。故人様のお子様が4人で、全員が男の子という賑やかなご家庭。さらにその子供たち、故人様のお孫様が13人と、本当に大家族でした。4人のご兄弟は本当に仲が良く、それぞれが津市や四日市に住まわれながらも、頻繁に実家へ集まっていたそうです。お盆や正月に限らず、鍋や焼き肉を囲んで集まる機会も多く、13人のお孫さんたちもまた、とても仲が良く、今回のお葬儀の期間中も常に「わちゃわちゃ」していて、私自身も皆様の仲の良さをとても感じました。
喪主様の奥様も、「こんなに仲の良い家族、本当にうらやましい」とおっしゃっていたのが印象的でした。
故人様は2年前にご主人を亡くされており、喪主様が「やっと自分の生き方ができると思ったところだった」と語られたように、長年にわたり、家族のために尽くしてこられた方でした。昭和の父親像を体現するご主人を支え、ご自身はその陰で家庭を守る役割に徹しておられました。

ご主人が単身赴任中には、「ママさんバレー」に打ち込んだり、土日は開放的に過ごされたりと、ささやかな楽しみを大切にされていたそうです。鼻歌まじりに「ルルル」と口ずさみながらよく働かれていたとのこと。その姿からは、誰かのために動くことが自然であり、喜びでもあったことが伝わってきます。
また、故人様は「下宿屋のおかみさん」としての顔もお持ちでした。高田短大や三重短大の学生たちを受け入れ、約10人もの世話をしながら、お子様たちの育児や教育にも力を尽くされました。ご自身の家庭だけでなく、若い世代の成長も支え続けた日々は、まさに献身の人生でした。
ご主人が60歳頃から神主として約20年間奉仕された間も、その準備や手伝いに努められ、ご主人の活動を支えることが生活の一部だったそうです。喪主様が「母は自分で決めることはほとんどなかった。でも、それで良かったのかもしれない」と語られるその姿には、静かな誇りが感じられました。
ご主人が先立たれた後は、一気に元気をなくされたそうです。深く寄り添って生きた年月があったからこそ、喪失の悲しみも深いものだったのでしょう。やはり、故人様はご主人のことが大好きだったんだと思いました。ご主人が病気になり、亡くなる2~3年前、お家の神社である伏見稲荷に、故人様と子供たち、お孫様たちでお参りに行ったそうです。伏見稲荷は山の上にあるのですが、故人様がものすごい勢いで、一番速く、力強く登り、みんなは付いていくのに必死だったというお話も聞かせていただきました。
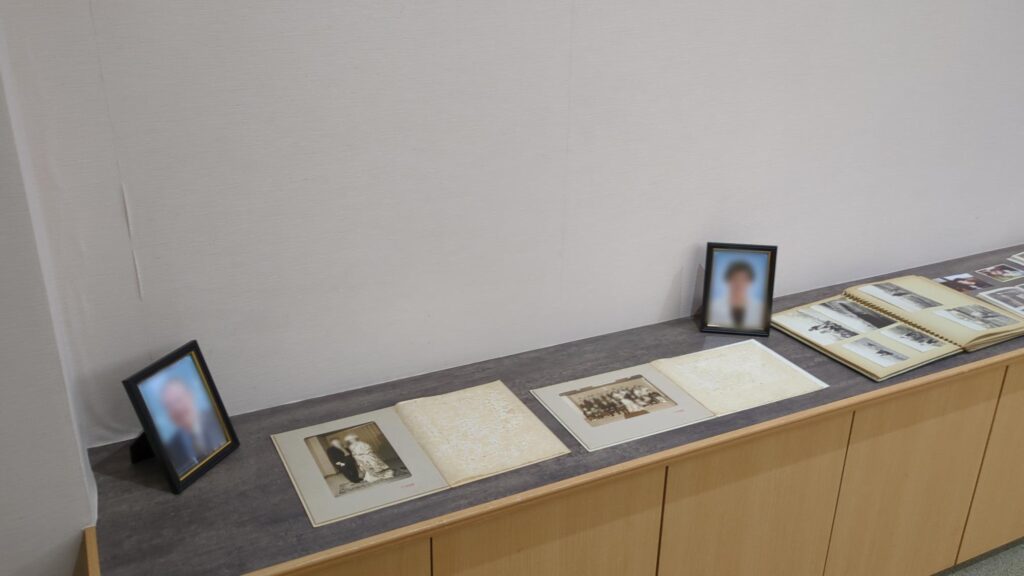
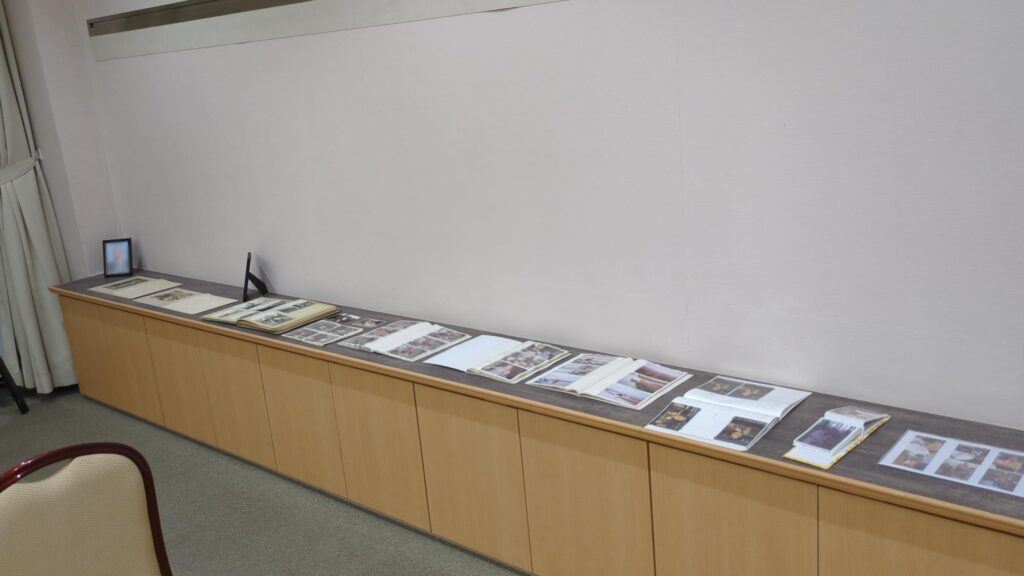
60歳を過ぎてから習字教室に通い、毎年書道展にも出品されていたそうです。その作品を式場に飾らせていただきました。10年分の作品はまさに圧巻でした。

お家の方々も、習字をしていたのは知っていたが、作品を見るのは初めてで、同じ書体だけではなく、さまざまな表現があり、「こんなにたくさんの作品があったなんて」と、ご覧になられながら驚かれていました。
また「なんて書いてあるんだろう?」とじっくり眺めたり、「これってどういう意味?」と言葉の意味をスマホで調べたりする姿もありました。


お孫様たちにもお話を伺いました。故人様は特別な存在で、やさしく、元気、よく笑っていたそうです。
集まりのときにはくじ引きや、お楽しみボックス、腕相撲大会、ゲームなど、いつも皆を喜ばせようと準備をしてくれていたそうです。
また、小さい頃、遊びに行った時には、台所でお菓子を探し回り、みんな食べてしまうので、すぐに無くなってしまう。故人様が見つからないようと、別の場所に隠してもまた、見つけ出して食べてしまう。「お前たちが来るとお菓子が全部なくなる!」と笑いながら、頭を「コツン」と注意されたこともあったそうです。
ほかにも、故人様が、買い物に行く時には、自転車の前のかごに乗せてもらったり。など、愛らしいエピソードをたくさん聞かせていただきました。
ご葬儀の最後に喪主様が語られた言葉が、今も心に残っています。
「最後におばあちゃんの言葉を代弁させていただきます。『みなさんに囲まれた人生を送れて、本当に幸せでした。ありがとう』」
この言葉には、故人様の人生とご家族様の思いが凝縮されていました。
ご葬儀を終えて、私自身も多くのことを感じました。皆様から故人様のお話をたくさん聞かせていただき、少しだけ大家族の一員になれたような気持ちになりました。お手伝いできたことを、心からありがたく思っております。
この度は大切なひとときを共にさせていただき、誠にありがとうございました。ご家族の温かい絆と、故人様の穏やかな生き方に触れることができ、感謝しております。

2025年7月21日 T家様(担当:山本)





