家族葬で受付が必要になるケース|依頼する相手・基本的なやり方も解説

家族葬は、親族や故人と親しい関係者を中心に執り行う葬儀で、場合によっては受付が必要になるケースもあります。
しかし、実際に家族葬の受付係を決めるとなると、「誰に依頼するのが適切なのか」と悩んでしまう方もいるでしょう。
この記事では、家族葬の受付について、必要になるケースや具体的な依頼する相手を踏まえながら解説します。
家族葬における受付のやり方やよくある質問もあわせて紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次

家族葬でも受付は必須?
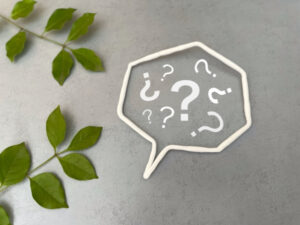
家族葬において、受付は必須というわけではありません。
ただし、同じ家族葬でも規模は異なるため、状況によっては受付の用意が必要です。
ここでは、家族葬の受付について、以下の2ケースを紹介します。
- 受付がなくても問題がないケース
- 受付があったほうがよいケース
それぞれ詳しく見ていきましょう。
また、家族葬の準備や一般葬との違いについて詳しく知りたい方は、下記の記事も合わせてチェックしてください。
【関連記事】家族葬の準備とは?一般葬との違いや事前に準備するものをわかりやすく解説
受付がなくても問題がないケース
受付がなくても問題がないのは、参列者が兄弟といった親族のみの場合です。
よく知る間柄かつ少数かつであれば、事前に喪主が全員を把握できます。
受付を設ける必要がなければ、精神的・経済的な負担を抑えられるため、メリットの1つです。
しかし、香典のやり取りには注意が必要になります。
喪主が直接やり取りできれば問題ありませんが、人数によっては管理が困難です。
受け取りが難しいと判断した場合は、事前に香典を辞退する旨を参列者に対して連絡してください。
規模が小さく参列者を全員把握できる際は、受付を設けないことも選択肢として検討しましょう。
受付があったほうがよいケース
受付があったほうがよいのは、参列者が多い場合やあまり親交・面識のない方を複数人呼ぶ場合です。
葬儀後には香典返しを贈るため、参列者を把握しておく必要があります。
しかし、受付がないために参列者の確認漏れや、間違いが生じてしまうのは失礼です。
親族だけで執り行う家族葬であっても、参列者が多いと喪主が全員を正確に把握しきれません。
会う機会がほとんどなく、お互いに顔もあまり認識できていない場合もありえます。
また、故人と親しかった友人・知人などを呼ぶ場合にも、参列者の確認漏れを防ぐためには受付があると安心です。
参列者の人数や内訳に応じて、受付の有無を決めましょう。
家族葬の受付係は誰がやるべき?

受付を置く場合、記帳や会場案内を1人ですべて行うのは大変です。
参列者の人数によっても変わりますが、受付係の適切な人数は2人が目安になります。
受付係を依頼する具体的な相手は、以下に挙げる3つが候補です。
- 孫や甥
- 血縁者以外の関係者
- 葬儀社のスタッフ
それぞれ詳しく見ていきましょう。
なお、斎奉閣では故人やご家族様の意向に沿った、家族葬を執り行えます。
葬儀に向けた事前準備を始めたい方は、ぜひ一度ご相談ください。
依頼する相手①:孫や甥・姪
受付係を依頼する相手としては、一般的に孫や甥・姪の場合が多く見られます。
孫や甥・姪は血縁的に遠すぎず、かつ声をかけやすいためです。
親族の中では年齢の若い場合が多く、初めてでも作業の飲み込みが早いと考えられるのも、理由の1つに挙げられます。
まずは、孫や甥・姪の中から受付の適任者がいないか探しましょう。
依頼する相手②:血縁者以外の関係者
親族は故人を失ったばかりで、精神的にも苦しい状況であることを踏まえると、血縁者以外の関係者に依頼するのも1つの手段です。
受付係については、親族がやらなければいけないという決まりはありません。
親族が普段からお世話になっている人物や、故人が勤めていた会社の関係者など、信頼のおける方に依頼してください。
心の整理がまだついていない親族には葬儀に集中してもらえるよう、血縁者以外の関係者に依頼することも検討しましょう。
依頼する相手③:葬儀社のスタッフ
親族や関係者で受付係の用意が難しい場合は、葬儀社のスタッフに依頼してください。
葬儀までにはさまざまな手続きや準備を伴うため、受付係の用意まで手が回らない場合も起こりえます。
無理に受付を担当したことで、葬儀に集中できなければ本末転倒です。
安心して葬儀を迎えられるよう、プロのスタッフに受付係を依頼するのも選択肢に入れましょう。
家族葬における受付のやり方
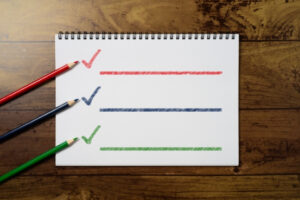
家族葬における受付のやり方は、以下の手順です。
- 参列者へ挨拶する
- 香典を受け取り、金額を記帳する
- 参列者に芳名録へ記入してもらう
- 返礼品を渡す
- 供物や香典を会計係に渡す
- 荷物や上着を預かる
- 会場へ案内する
故人を偲ぶ大切な式のため、丁寧で落ち着いた対応を心がけてください。
家族葬の終了後には、出棺・火葬への案内や、預かった荷物を返却する必要があります。
スムーズに進められるよう、準備の段階で受付の流れや不明点などは確認しておきましょう。
一般的な受付開始の時間や全体の流れについて知りたい方は、下記の記事も参考にしてください。
【関連記事】【シーン別】家族葬にかかる時間|短縮して負担を軽減する方法も解説
家族葬の受付に関するよくある質問

家族葬の受付に関するよくある質問は、以下の2つです。
- 受付で挨拶する際の言葉は?
- 【参列者の場合】受付なしの場合に香典を渡すタイミングは?
それぞれ詳しく見ていきましょう。
質問①:受付で挨拶する際の言葉は?
受付では「お忙しい中お越しいただきありがとうございます」という感謝の言葉で、参列者に挨拶します。
故人を偲ぶ場となるため、笑顔は控え落ち着いたトーンでの挨拶を心がけてください。
また、「忌み言葉」を使わないよう注意が必要です。
「重ね重ね」や「再び」などの忌み言葉は悪いことや不幸の繰り返しを連想させかねないため、避けるようにしてください。
質問②:【参列者の場合】受付なしの場合に香典を渡すタイミングは?
受付がない場合に香典を渡すタイミングは、喪主に挨拶するときです。
「このたびはご愁傷さまでした」と、お悔やみの言葉を添えて渡してください。
喪主が忙しく挨拶するタイミングも伺えないのであれば、帰る際や遺族に渡しても構いません。
周りの状況も見計らいながら、挨拶とあわせて香典を渡しましょう。
家族葬の受付でお困りの方は

家族葬における受付の有無や依頼する相手を急遽決めるのは、遺族にとっても負担がかかってしまいます。
家族葬の受付は、必ずしも親族が担当する必要があるというわけではありません。
必要に応じて、プロに依頼するのも選択肢の1つになります。
なお、斎奉閣は三重県内で22会館を展開し、葬儀施行数No.1(※)の実績を誇る地域密着の斎場です。
※当社調べ/2022年1月~12月の四日市市、いなべ市、東員町、桑名市、菰野町、亀山市、津市、名張市、伊賀市内の斎奉閣・和ごごろ22会館合計葬儀施行数
家族葬の受付でお困りの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
まとめ:家族葬の受付について

家族葬の受付は、参列者の人数や規模に合わせて設置の有無を決めます。
親族や関係者に依頼する場合は、信頼のおける方に受付をお願いしましょう。
なお、斎奉閣では葬儀に関する無料事前相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
無料事前相談受付中
- 残された家族の負担を減らす
- 死に対する
不安解消 - 遺産相続のトラブルを回避できる
「事前準備を始めたいけど何から始めればわからない…」という方はお気軽にご相談ください。
この記事の監修者
【関連記事】参列者5人以下でも家族葬はできる?費用相場や人数を減らすメリットを解説
【関連記事】家族葬は読経なし・戒名なしでもできる?メリットや注意点を解説
【関連記事】家族葬の斎場とは?種類や選び方、費用についてわかりやすく解説
お葬式について
家族葬











