【火葬式の流れ】必要な手続き・書類とともに解説|選ばれる理由や注意点も

火葬式は一般葬とは異なり、短い時間で執り行えるため、近年注目されている葬儀のスタイルです。
そのため、葬儀の形式を検討する際に、選択肢の1つとして挙げる方も少しずつ増えています。
平均寿命が伸びて喪主の高齢化が進む現代では、心身の負担を軽減できる火葬式が、重要な役割を果たしています。
しかし、「火葬式はどのような流れで進めるのか」と疑問に思う方も多いでしょう。
この記事では、火葬式の流れや必要な手続きを解説します。
火葬式が選ばれる理由や注意点もあわせて紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次

火葬式とは

火葬式とは、通夜や告別式を執り行わない葬儀の形式です。
ここでは火葬式の基礎知識として、以下の3つを解説します。
- 特徴
- 直葬との違い
- 火葬式を選ぶ方が増えている理由
それぞれ詳しく見ていきましょう。
特徴
火葬式の特徴は、以下のとおりです。
- 費用を安く抑えられる
- 短時間で執り行える
- 故人を静かに見送れる
一般葬では1日目に通夜、2日目に告別式を執り行います。
しかし、火葬式では通夜や告別式が省かれ、時間を大幅に短縮できるうえに費用を抑えることが可能です。
また、参列する人数が少なく、故人を静かに見送れます。
このような特徴から、火葬式はシンプルな葬儀を望む方に適しています。
直葬との違い
火葬式と直葬は基本的に同じ意味で執り行われますが、一部の地域や葬儀社では下表のように区別されることもあります。
|
火葬式 |
直葬 |
|
・ご遺体を安置する |
・ご遺体は火葬場へ直接運ばれる |
葬儀形式として区別される場合の大きな違いは、面会時間の有無です。
火葬式では故人と面会できるため、最期の時間をゆっくりと過ごせます。
残されたご家族が気持ちを整理して新しい生活を踏み出すうえで、最期の時間は重要な意味を持ちます。
葬儀の形式を選ぶ際は内容を確認し、重視するポイントを話し合っておきましょう。
火葬式を選ぶ方が増えている理由
火葬式を選ぶ方が増えている理由は、以下のとおりです。
- 葬儀を担う世代の高齢化
- 地域社会からの孤立化
- 世帯構造の縮小
2024年の平均寿命は男性81.09歳、女性87.14歳となっており、喪主の高齢化が顕著です。
また、世帯構造にも変化がみられています。
2020年の統計では単身世帯が38.0%と最も多く、夫婦と子の家族構成は減少傾向です。
このことから、世帯構造はますます縮小すると予測されています。
地域社会のつながりは希薄化しており、現在の社会状況下では経済面や心身の負担を考慮した葬儀の形式を選択することが重要です。
火葬式は多様な課題に対応した選択肢の1つとして有効であり、今後も増加する可能性があるでしょう。
引用元:
・厚生労働省|令和5年簡易生命表の概況 主な年齢の平均余命
・国立社会保障・人口問題研究所|日本の世帯数の将来推計(全国推計)
【最短2日】火葬式の流れ

火葬式の流れに含まれる工程は、以下の5つです。
- ご遺体を搬送・安置する
- 葬儀の打ち合わせを行う
- 死亡届を提出し、火葬許可証を受け取る
- 納棺・お別れのあとに火葬する
- 埋葬許可証を保管する
火葬式は最短2日で終了しますが、これには法的な理由があります。
仮死状態かどうかを判別するため、亡くなってから24時間経過しなければ、火葬や埋葬は行えないと法律で定められています。
火葬式における、それぞれの流れを見ていきましょう。
流れ①:ご遺体を搬送・安置する
火葬式を執り行う際も一般の葬儀と同様に、まずはご遺体を搬送・安置します。
病院や施設で亡くなった場合は、ご遺体を安置する場所まで葬儀社が搬送するため、依頼の連絡が必要です。
安置場所はさまざまで、葬儀社に依頼できるケースもありますが、費用が発生したり制約があったりする点に留意してください。
自宅で安置するときは、ご遺体が傷まないよう室内の温度に注意が必要です。
火葬場が混んでいれば、火葬式を執り行う際に想定よりも時間がかかる可能性もあります。
そのため、ドライアイスの確保など、ご遺体の保管に関して葬儀社と相談しておきましょう。
流れ②:葬儀の打ち合わせを行う
火葬式を執り行う際、一般的には葬儀社と打ち合わせを行います。
打ち合わせでは、火葬の日程や必要なサービスの選択などを検討します。
火葬式は一般葬よりもシンプルで、打ち合わせにかかる時間も短く済むでしょう。
ただし、打ち合わせの際に提示される見積もりの内訳は、入念に確認することが大切です。
葬儀社のサービス内容や選ぶ際の注意点を知りたい方は、下記の記事を参考にしてください。
【関連記事】葬儀屋と葬儀社の違いは?4つの種類や選ぶ際の注意点をわかりやすく解説
流れ③:死亡届を提出し火葬許可証を受け取る
火葬式を行うためには死亡届の提出や火葬許可証の受理など、役所での手続きが必要です。
届出の手続きは、火葬式の重要なステップです。
まず、医師によって作成された死亡診断書とともに、死亡届を役所に提出します。
死亡届の提出期限は、死亡した事実を知った日から7日以内です。
火葬式を選択した場合でも手続きは不可欠となり、ご家族にとっては心身の負担となる可能性があります。
葬儀社が火葬式に関する手続き代行を行う場合もあり、事前に確認しておくことが大切です。
なお、死亡診断書は「死亡の事実を証明する書類」で、保険金などの請求時に必要です。
大切な書類となるため、コピーしておくとよいでしょう。
流れ④:納棺・お別れの後に火葬する
火葬許可証を受け取ったあとは、納棺・お別れを行い火葬に進みます。
このとき、ご遺体の身支度を整えて棺に納め、お別れの際に花や思い出の品を入れ、故人への敬意と感謝を示す点は一般式と同様です。
火葬式では参列者が少ない分、故人と静かに最期の時間を過ごすことが可能です。
火葬後は、お骨を箸で拾い骨壺に納める「お骨上げ」を行うため、マナーを覚えておくと役立ちます。
骨上げのやり方やマナーについて知りたい方は、下記の記事を参考にしてください。
【関連記事】お骨上げとは?やり方やマナー、拾骨と収骨の違いについて紹介
流れ⑤:埋葬許可証を保管する
火葬式では、終了すると埋葬許可証が交付されます。
火葬の完了を示す公的な書類で、骨壺と一緒に桐の箱に入れてあることが一般的です。
埋葬許可証には火葬済みの印が押されており、後日納骨する際に必要となります。
火葬式の手続きを確実に行うためにも、この証明印が押されているかを確認しておくと安心です。
遺骨の納骨は、四十九日の法要が終わった際に行われることが多くなります。
ただし、新しくお墓を立てる場合は、一周忌などに行うケースも少なくありません。
埋葬許可証は受け取ってから納骨までに期間が空くため、紛失しないようしっかりと保管しておきましょう。
万が一紛失してしまった場合、再交付の手続きは死亡届を提出した役所でのみ可能な点に注意してください。
火葬式を執り行う際の注意点

火葬式を執り行う際の注意点は、主に以下のとおりです。
- 故人の関係者へ丁寧に説明するなど配慮する
- 親族の理解と同意を得る
- 菩提寺の理解を得る
- 火葬式にかかる費用を明確にする
火葬式は、故人と親しかった方々にとって、お別れする機会の限られる形式となります。
そのため、親族や故人の友人には、火葬式にする理由を説明して理解を得ることが大切です。
必要であれば、後日お別れの会を開催するなどの対応をおすすめします。
菩提寺への対応も重要です。
作法に則って葬儀を執り行わないと納骨を断られるケースもあるため、あらかじめ確認しておきましょう。
また、費用を抑える目的で火葬式を選択したのに、オプションが追加されて予定額を大幅に超えるケースも少なくありません。
葬儀社と綿密に話し合い、内訳を提示してもらうことが大切です。
なお、火葬式で発生しうるトラブルは、直葬と共通するものも多くあります。
直葬のトラブル内容や対処法を詳しく知りたい方は、下記の記事を参考にしてください。
【関連記事】直葬でよく起こるトラブル5つ!対策や対処法をわかりやすくご紹介
火葬式を選ぶか悩んでいる方は
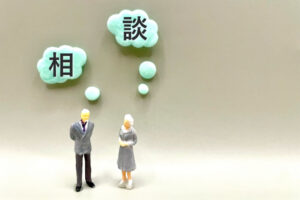
火葬式を選択する際は周囲の理解が不可欠となり、慎重な検討が必要です。
残されたご家族が判断に悩まないためには、ご自身の希望を明確にしておくことが重要です。
たとえば、エンディングノートに希望を記載しておけば、亡くなったあとの対応がスムーズに進みます。
終活によって老後生活を明るく過ごしている方の声などは、こちらの動画で紹介していますので、ぜひご覧ください。
なお、葬儀形式で火葬式を選ぶか悩んでいる方には、斎奉閣がおすすめです。
斎奉閣は火葬式が選択できる葬儀場で、三重県内で22会館を展開しています。
葬儀施行数No.1(※)の実績を誇り、その経験から個々の悩みに寄り添い適切な提案をいたします。
※当社調べ/2024年1月~12月の四日市市、いなべ市、東員町、桑名市、菰野町、亀山市、津市、名張市、伊賀市内の斎奉閣・和ごごろ22会館合計葬儀施行数
火葬式をトラブルなく進めたい方は、ご葬儀の種類ページをぜひご覧ください。
まとめ:火葬式の流れは一般葬よりもシンプル

火葬式の流れは一般葬よりもシンプルであり、その分時間を大幅に短縮できます。
ご家族や親族の負担軽減にもつながり、大きなメリットといえるでしょう。
なお、斎奉閣では火葬式の経験も多く、適切なアドバイスが可能です。
葬儀に関する負担を軽減し、火葬式をスムーズに執り行いたい方は、ご葬儀の種類ページをご覧ください。
この記事の監修者
【関連記事】火葬とは?持っていくものや流れ、時間などについてわかりやすく解説
【関連記事】家族葬の準備とは?一般葬との違いや事前に準備するものをわかりやすく解説
【関連記事】直葬の流れを6つのステップで解説!直葬を選ぶ割合やメリット・デメリットを紹介
お葬式について











